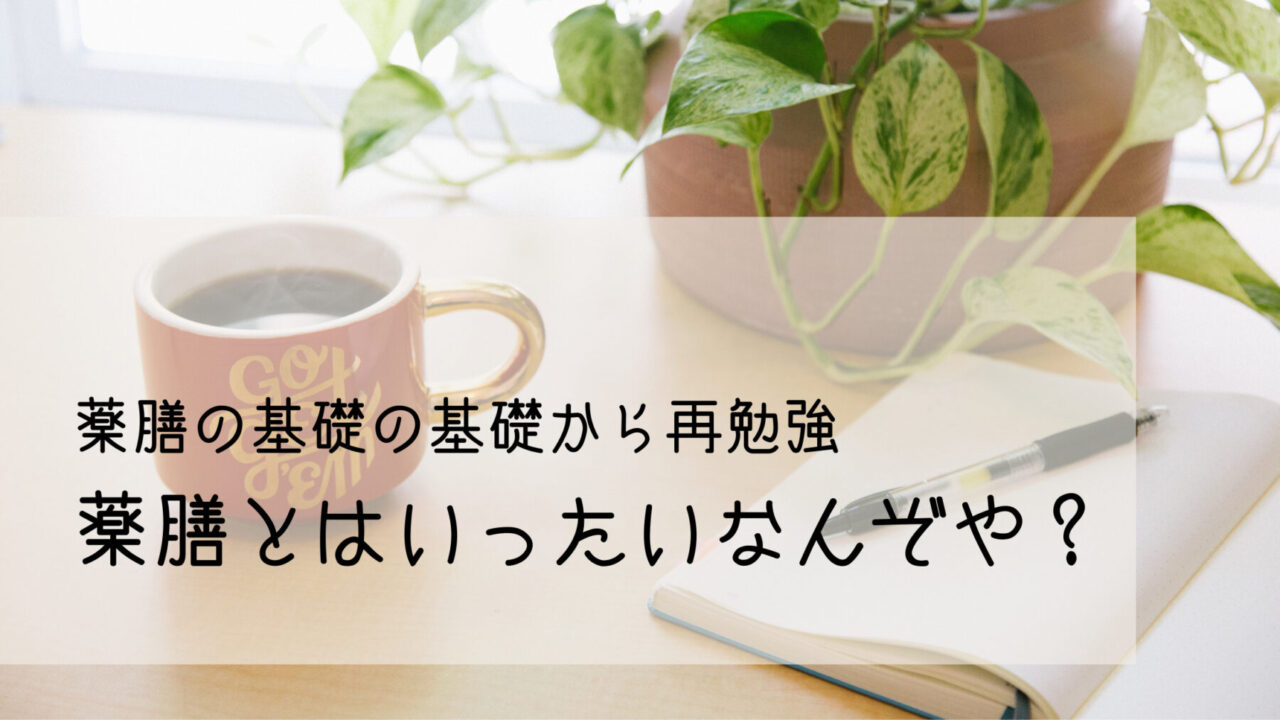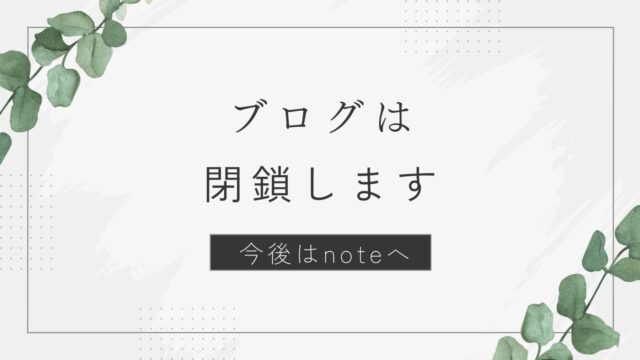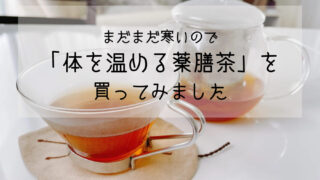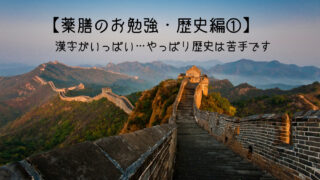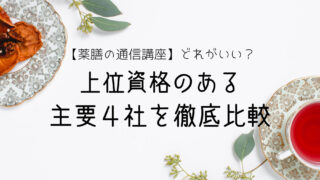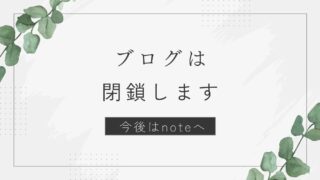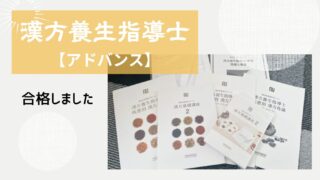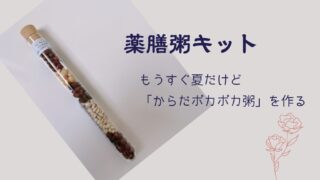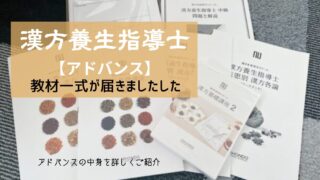こんにちは。管理栄養士&薬膳アドバイザーのミントです。
すでにアドバイザーの資格を持ってはいますが、もっとちゃんと薬膳の勉強をしようと学び直しを始めたところです。
何も基礎の基礎からやらんでも・・・とは思いますが、
じゃあどこから始める?ってなるので。
今回は基礎の基礎、薬膳とはなんぞやというお話をまとめてみました。
サクッと読んでいただけると幸いです。
初歩の初歩 薬膳ってなんぞや
薬膳の定義

薬膳の始まりははっきりしないようですが、中国には少なくとも3000年以上前からすでに薬膳の起源となる「食養」「食療」といった考え方があったそうです。
食養:
病を持っていない人に対して、食材の効能を生かし、食事で病気の予防や健康増進を図る
食療:
病を持っている人に対して、食材の効能を生かし、食事で病気の回復や症状軽減を図る
その後加わった「伝統的薬膳」の概念としては
薬膳:
「食療」に生薬(中薬)を加えて作る、病を治すための料理のこと
※本によっては、生薬は中薬と呼ばれています
生薬とは
自然界に存在する天然の植物(根・茎・葉・実・花など)動物(骨・皮・昆虫など)鉱物由来のものなどを乾燥させたり焙じたりして作った薬のこと。
加工せずそのまま使用するものもある。
ただ現在では、
健康増進や病気の予防・治療・症状軽減を図る食事のことを全てまとめて「薬膳」と呼んでいます。
↓↓↓
薬膳とは
中医学の理論に基づき、食材や生薬(中薬)を組み合わせて作る料理
健康維持や病気の予防・治療を目指す食事
大事なのは「中医学の理論に基づく」というところで、単に生薬を使ったら良いというわけではありません。
では、中医学ってどんなものなのか・・・
奥深いので一言で表現するのは難しいですが、
中医学とは
中国の歴史・天文学・地理学・気象学・哲学思想の影響を受けながら臨床経験を積み重ね、中国独自で発展した医学
この中医学の理論に基づき
それぞれの体質や体調・症状および季節や土地などを考慮した食材や生薬を組み合わせて作る料理が「薬膳」です。
哲学ってなかなか理解するのが難しいですよね・・・(ちょっと拒否反応😅)
中医学は本当に奥が深い。
もちろん全部を理解することなんて不可能なので、少しずつざっくり勉強していきたいと思います💦
「薬食同源」という考え方

薬食同源とは
生薬も食材も根本的には同じであり、すべての食物には薬のような効能がある。
それゆえに食材も上手に食べれば体調を整えたり健康を保つことに役立つが、食べ方を間違えれば病を起こすこともある・・・という考え。
献立を立てる際、栄養士としてはついついカロリー計算だけやっちゃいそうですが💦
季節や体調に合わせて食材を選ぶということも大切なことですね。
ところで漢方と中医学のちがいは?

私が今一番気になっている資格は「漢方養生指導士」であることを、前回記事にしました。
⇒漢方養生指導士の資格が気になっています
その「漢方」とはいったい何なのか・・・という話ですが。
漢方とは
「漢の国から伝来した医学(中医学)」が日本独自に発展を遂げたもの
日本では、東洋の伝統医学を総称して「漢方」と呼ぶ
江戸時代、オランダのことを漢字で「和蘭」と書いていたので、オランダ人から伝わった西洋医学を「蘭方」と呼んでいました。
古くから日本に伝わる医学と、この「蘭方」を区別するために生まれたのが「漢方」という言葉です。
漢方のルーツは中医学ですが、日本独自の考え方をプラスして発展した医学なので、診断方法や治療の方針は大きくちがいます。
土地や気候だけでなく、日本人の体質や・味の好みなど、そりゃ中国人とはちがうので、日本人に合わせたものに変わって行くのは当たり前ですね。
では西洋医学と中医学のちがいは何?

そもそも日本の伝統医学といえば「漢方」だったところに、江戸時代『解体新書』が出版され、西洋医学の普及が加速したといわれています。
1875(明治8)年には明治政府が西洋医学を取り入れることを決め、日本の医学は西洋医学中心へと変わって行ったんですね。
そんな西洋医学と中医学、ちがいは何なんでしょうか?
西洋医学
西洋医学の特徴
科学的根拠に基づいた医療
投薬や手術といった方法で、体の悪い部分に直接アプローチして治療する「対処療法」である
短い時間で病気を治療できる
管理栄養士の私が学んできた栄養学も、西洋学に基づく食事管理法です。
1日に必要なカロリーの計算をして、各種栄養素をバランスよくとることが最重要視されています。
その人の年齢や体型・体調・環境などに合わせたオーダーメードの食事療法をしてきたつもりですが・・・
薬膳を勉強すると、土地や季節、体質や味なども考慮することで、さらに奥深いオーダーメードの食事療法ができるな…と思います。
中医学
中医学の特徴
体の不調を内側から根本的に治す治療法
症状が現れている部分だけでなく、体全体の歪みや季節なども考慮して診断・治療する(鍼灸・あん摩・薬膳・漢方薬など)
また、病気でも健康でもない「未病」を防ぎ、治すことを大切に考える
治療には時間がかかるが、体に負担はかかりにくいとされる
西洋医学では検査で異常が見つからなければ診断が進まず、治療も始まりません。
病院勤務をしていた私は当時、内科回診にも参加してたのですが、
「この患者は検査では異常がなく、原因不明の倦怠感で現在精査中です」という医師の言葉をよく聞きました。
(しんどそうなのに、どこにも異常がない…なぜ?)という患者さん、結構多いですよね。
中医学では検査で異常があろうがなかろうが、不調を感じるならどこかに悪いところあるという考えなので、
体質に合った食材や生薬を探し、心身のバランスを整えていきます。
病院で一栄養士がしゃしゃり出て、これを主張することは難しいとは思いますが、
栄養相談として患者さんに関わる際に、アドバイスくらいはできたかもしれないと今なら思います。
中西結合をめざして

じゃあどちらが優れているんだ?なんてことではなく。
中国だって現在では中医学と西洋医学の長所を融合させた医療「中西結合」を目指しています。
西洋医学の検査データーは中医学の診断にも使用できるし、
逆に西洋医学では治せないモヤっとした病気が中医学の処方で改善することもあります。(最近では病院でも漢方薬が処方されるようになっきましたよね)
中医学は西洋医学のように「科学的根拠に基づく」ものではないかもしれませんが、
「3000年という長い長い時間をかけて中国のめちゃくちゃ多くの人々が実践してきた結果」ではあるので、
中医学はある意味「実証済み」といえるのかもしれません。
ですが、今後は中医学の内容を科学的に解明することも実行されるでしょう。
そうなると、最強ですよね!
・・・っと、話が深いところまで行ってしまいましたので、今日はこの辺で。
薬膳とは まとめ

薬膳とは
- 中医学をベースにした日本独自の「漢方」の理論に基づき、食材や生薬(中薬)を組み合わせて作る料理
- 体質や症状・体調・土地・季節など、個人に合わせたオーダーメード食
- 心身のバランスを整え、健康維持や病気の予防・治療を目指す食事
対処療法といわれる「西洋医学」と予防医学といわれる「中医学」ですが
どちらも優れた医療に変わりはないので、良いとこ取りをすればいい!ということです。
管理栄養士としても「西洋医学+中医学」の知識を持って、より良い食事作りに貢献できたらなぁと思いました。