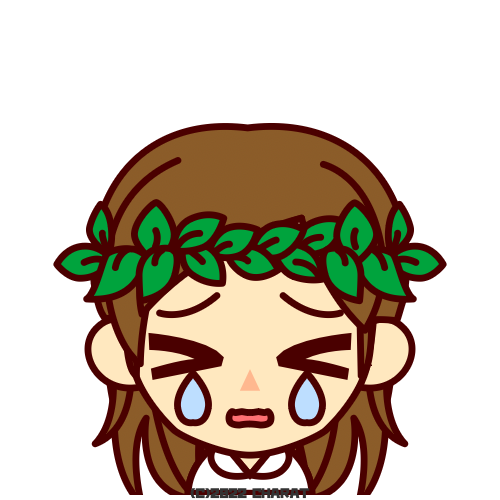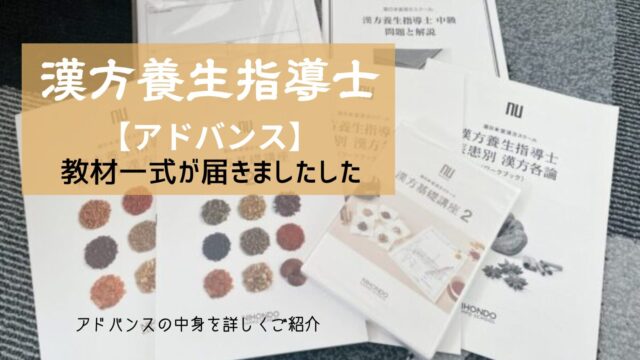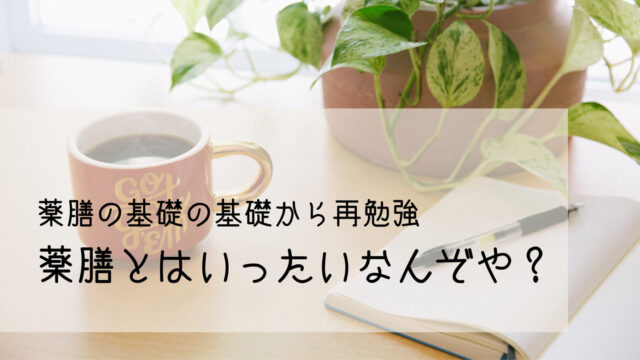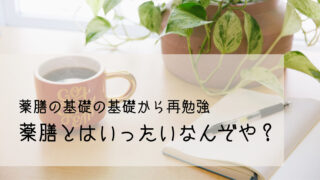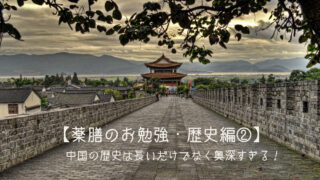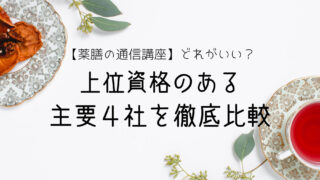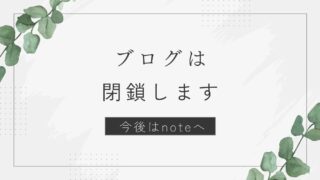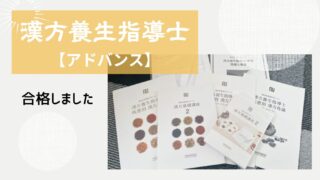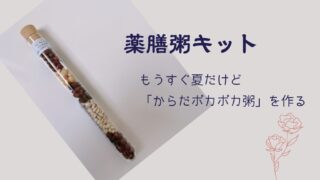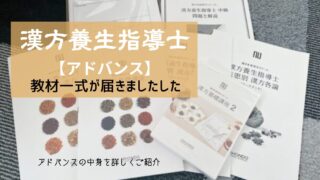こんにちは。管理栄養士&薬膳アドバイザーのミントです。
ただいま薬膳の勉強を再開したところです。
薬膳の勉強を始めると、どの本も最初に出てくるのは歴史
薬膳を学ぶにあたり、これ必要?って思っちゃうけど😂
やはりその起源と発展を理解し、歴史や哲学・文化まで勉強しなくては薬膳は語れないそうですね・・・
わからないからすぐ最初から勉強することになり、最初の最初だけを繰り返し勉強してしまうあるある・・・
日本史でいえば、縄文時代ばっかり繰り返しやってしまうパターンのヤツや。
歴史全体の内容をしっかりまとめて、次へ進まないとです。
今回は長い中国の歴史の中から「漢の時代」までをまとめております。
さて、何から覚えようか・・・
少なくとも3000年以上前から薬膳の考え方があった

前回の記事(薬膳とは)でも紹介しましたが、
薬膳の始まりははっきりしないものの、中国には少なくとも3000年以上前から薬膳の起源となる「食養」「食療」といった考え方があったといわれています。
中医学についての伝説は、それよりももっともっと昔・・・
石器時代の化石からは、石を使ってお灸のように体を温めたり按摩したり、石を磨いて針を作り医療道具として使ったりしていたんじゃないかっていう痕跡が見受けられるそうですよ。
古代文明😲
何だかものすごくロマンを感じる・・・
中国の歴史を振り返る
薬膳に関わる歴史を振り返り、自分なりにまとめて覚えていきたいと思います。

夏~商の時代
B.C.2100~1100年?
歴史が長すぎて、間が1000年もあるのにまとめられている(笑)
なので歴は書くのはやめることにします。
日本では「商」の時代を「殷いん」の別称としていることも多いようですが、中国では「商」が正式名称となっています。 こういうのもつまずくよね・・・
この時代に
- 火を上手に利用するようになり、調理技術が生まれ、食材を熱して食べることで胃腸障害をなくした
- 醸造技術が生まれ、食材を酒に漬けた薬酒をつくった
- 伊尹いいんという料理人が生薬の煎じ方を考案し、「湯液とうえき」をつくりはじめた
と言われています。
この時代から病名というものもできたようで、遺跡の甲骨文には疾病が記載されています。
灸や針・按摩、薬物で治療を行っていたというから驚きですね!
西周の時代

飲食や健康を重視する考えが確立したとされる時代です。
官僚制度が書かれた書物『周礼』によると、医療における職が設置されていたそうです↓↓↓
包人:厨房で働く人 30名+助手40名
膳人:王とその家族の食事を管理・検食(お毒見役) 32名+助手120名
医師:医療法や政策を受け持つ管理職 10名+助手20名
食医:王とその家族のために治療や予防効果のある食事を考案 2名
疾医:内科医 8名
瘍医:外科医 8名
獣医:4名
『周礼』の中での「医師」は管理職のことをいい、 医師の種類は食医・疾医・瘍医・獣医の4つに分かれます
赤色は食に関する職です。
関わる人数が合計224名ととても多く、食が重要視されていたことがよくわかりますね。
そして医師は食医・疾医・瘍医・獣医と4つに分かれていましたが、食医が最高位にあると記されています。
「食医」は王とその家族のために、飲食のバランス・四季の陰陽調和・味の配合を管理していたとか。
病気やケガの治療・予防は、薬や手術よりも毎日の食事でという考え方は、まさに薬膳ですね。
また中国最古の詩集である『詩経』には200種類以上の食材が記載され、「いくつかの薬草は食用にも薬用にもなる」と書かれているそうです。
医食同源の始まりの時代でした。
東周~春秋・戦国時代~秦の時代

始皇帝とかキングダムとか・・・そんな時代も苦手な私😅
部族社会から封建社会へ変化していき、
中国の歴史において、科学や技術など文明が著しく発達した時代でもあるとか。
この時代に書かれた『黄帝内経こうていだいけい』は、中医学の基礎理論の基となった経典です↓↓↓
黄帝内経
中国最古の医学書
「食養」や「食療」に関することを初めてまとめた書でもある
伝説の帝王「黄帝」と岐伯ぎはく など6人の医師との問答形式による医学書
「素問」と「霊枢」の2篇に分かれ、全18巻で構成
霊枢:経絡や鍼灸などが中心
素問:身体の生理と病理など理論的な内容
素問には五味調和や配伍・禁忌などについてすでに記載があり、薬や食材の組み合わせについての研究がされていたことがわかっています。
漢の時代

秦の始皇帝や漢の武帝などの権力者は、不老長寿を強く求めたんですって。
また、中国と中央アジアおよびヨーロッパを結ぶシルクロードで貿易を行ったことで、
さまざまな薬や食材が手に入るようになったことも薬膳の発展につながったようです。
この時代に書かれた『神農本草経しんのうほんぞうきょう』は中国最古の薬学専門書です↓↓↓
365種の生薬と食材を「上品」「中品」「下品」の3種に分類し詳しく説明
毒性の有無や毎日食べて良いかなどが明確にされた
| 上品 | 120種 | 毒性なし 多量に長期使用可 健康長寿 |
| 中品 | 120種 | 毒性あるものとないものがある 病気予防 虚弱を補う |
| 下品 | 125種 | 毒性あり 病気を治すために短期間の使用にとどめる |
また、「医聖」と呼ばれる張仲景ちょうちゅうけいによって書かれた『傷寒雑病論しょうかんざつびょうろん』は現在、中医臨床の経典となっています↓↓↓
「傷寒論」急性熱性病と「金匱要略」慢性病(雑病)の2冊に分かれている
薬物による治療法だけでなく、生薬と食材を組み合わせて作る薬膳についても詳しく記載されている
・・・とここで
長くなってしまったので、一旦終わりにしたいと思います。
歴史①のまとめ

| 商 |
|
| 西周 |
|
| 東周 春秋・戦国 秦 |
|
| 漢 |
|
3000年以上前から薬膳の考え方があった。
中医学の考えは1万年以上前の古代からあった。
さあ、もっと発展していく薬膳歴史・・・ここからがさらに難しくなる🤣
つづきは⇒【薬膳のお勉強・歴史編②】へ